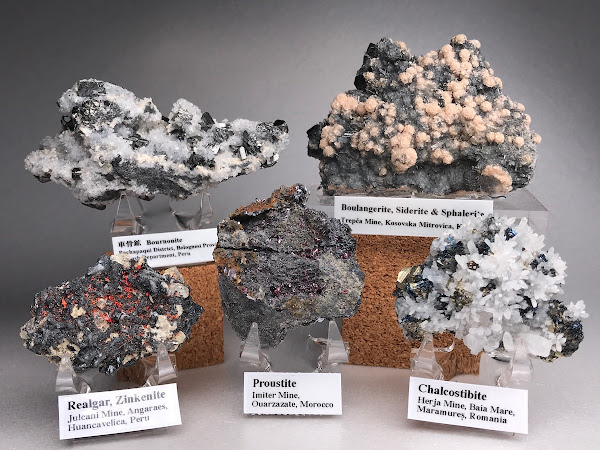石膏のいろいろなかたち Various Forms of Gypsum

1. 繊維石膏 Fibrous Gypsum Matsumine Mine, Odate City, Akita, Japan (秋田県大館市 松峰鉱山) Size: 105 × 83 × 63 mm / Weight: 657 g 透石膏(二水石膏の透明結晶)の標本はこのブログですでにいくつか紹介したところだが(たとえば これ や これ )、この標本は繊維石膏(fibrous gypsum または satin spar)の名で呼ばれていて、多数の石膏の結晶が、ある一方向に向かって一斉に成長して平行連晶したものとされる。こういう結晶成長のしかたは自然界では割とよくあるらしく、身近なところだと霜柱がそうだし、かつて耐火・断熱材としてつかわれた石綿は、ある種の蛇紋石や角閃石が繊維状に成長したものである。秋田県北東部の黒鉱鉱床に付随する石膏帯の産物。 Clear crystalline gypsum (selenite) specimens have been shown in this blog before. This piece of gypsum, called satin spar, shows a distinct texture caused by parallel growth of a number of crystals in one direction. The fibrous crystal habit often occurs in nature, which can be seen, for example, in frost columns and asbestos. It is from a gypsum deposit beside a kuroko (black massive ores containing copper, lead, zinc, etc.) deposit in the Northeast Akita. 別の角度から見た写真。 From different angles. 2. 雪花石膏 Alabaster Osabe Mine, Hinai-Machi Okuzo, Odate City, Akita, Japan (秋田県...